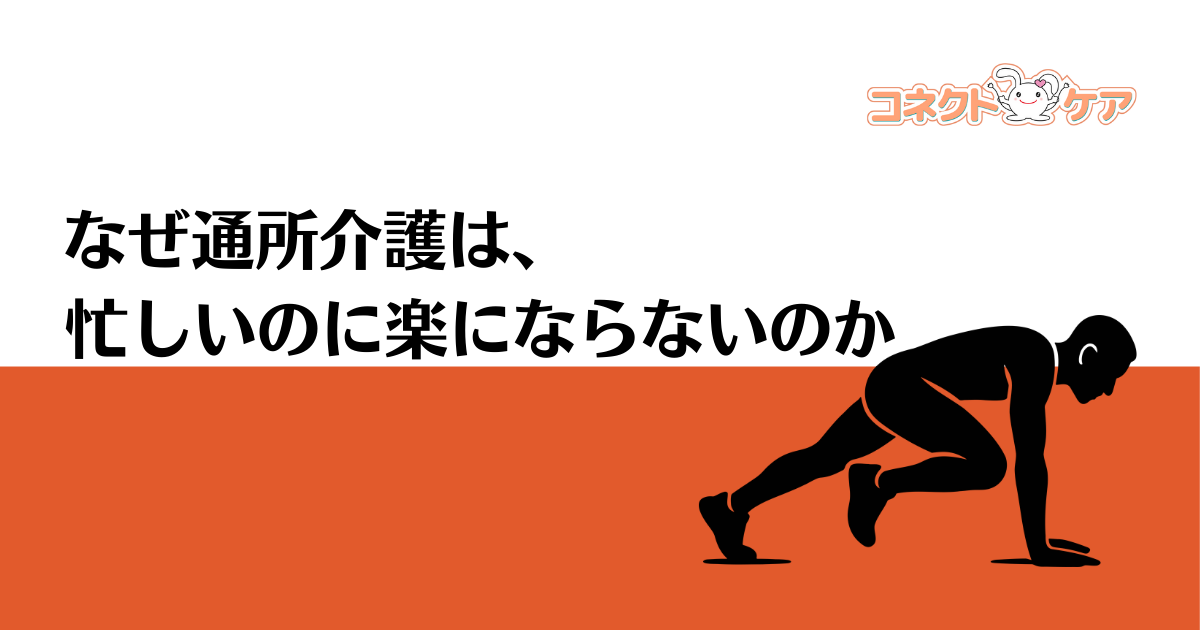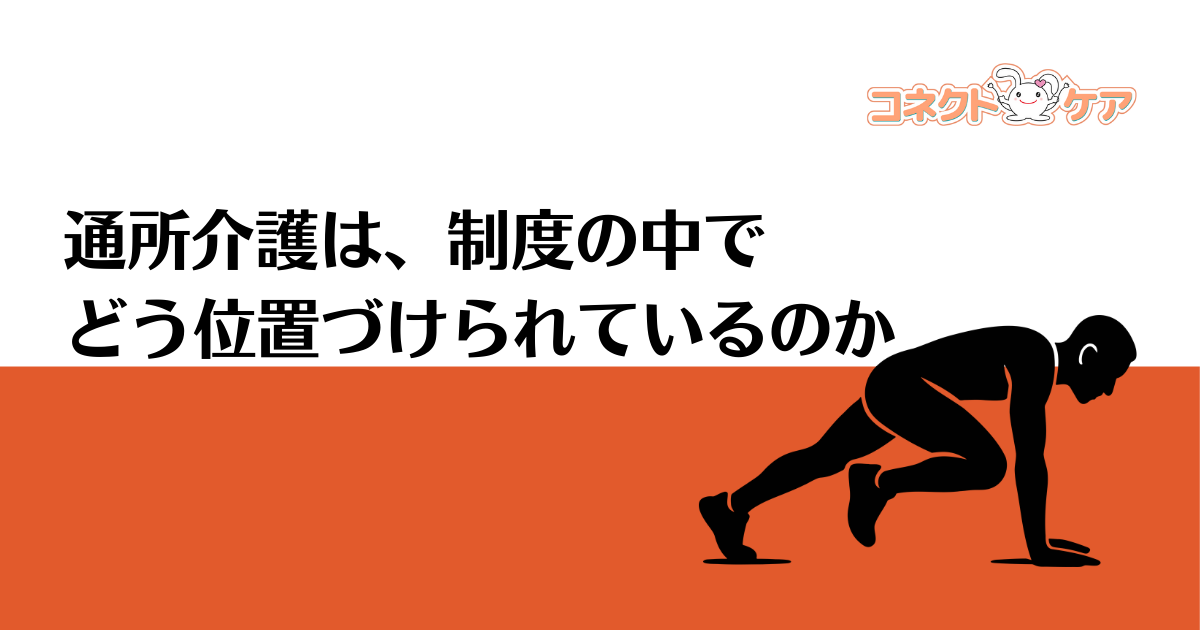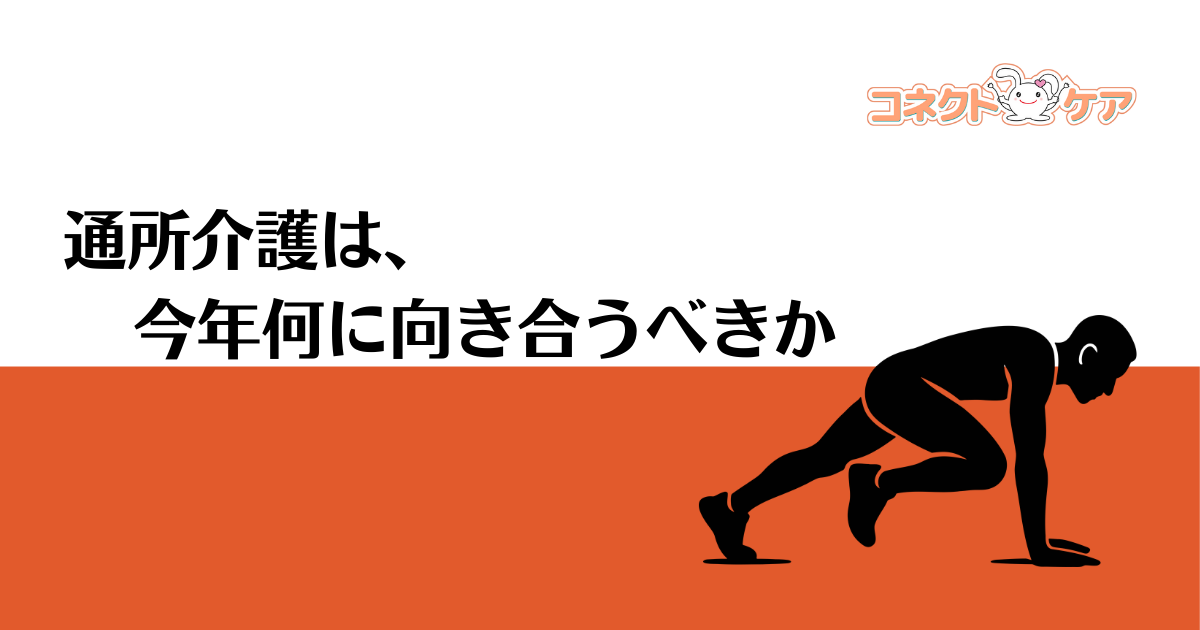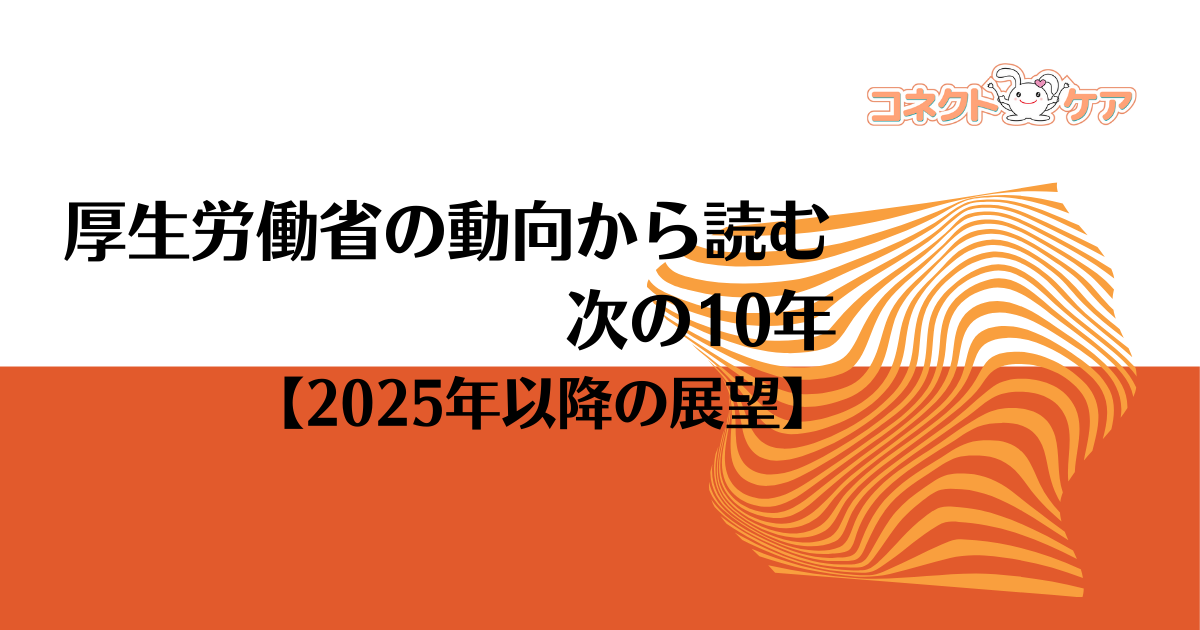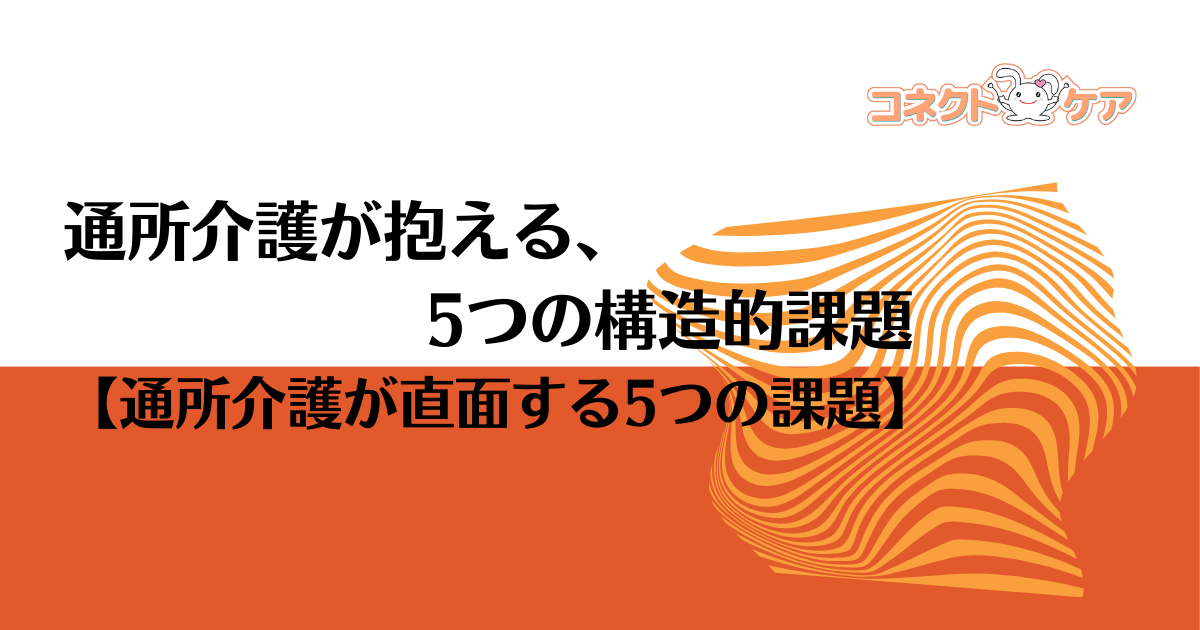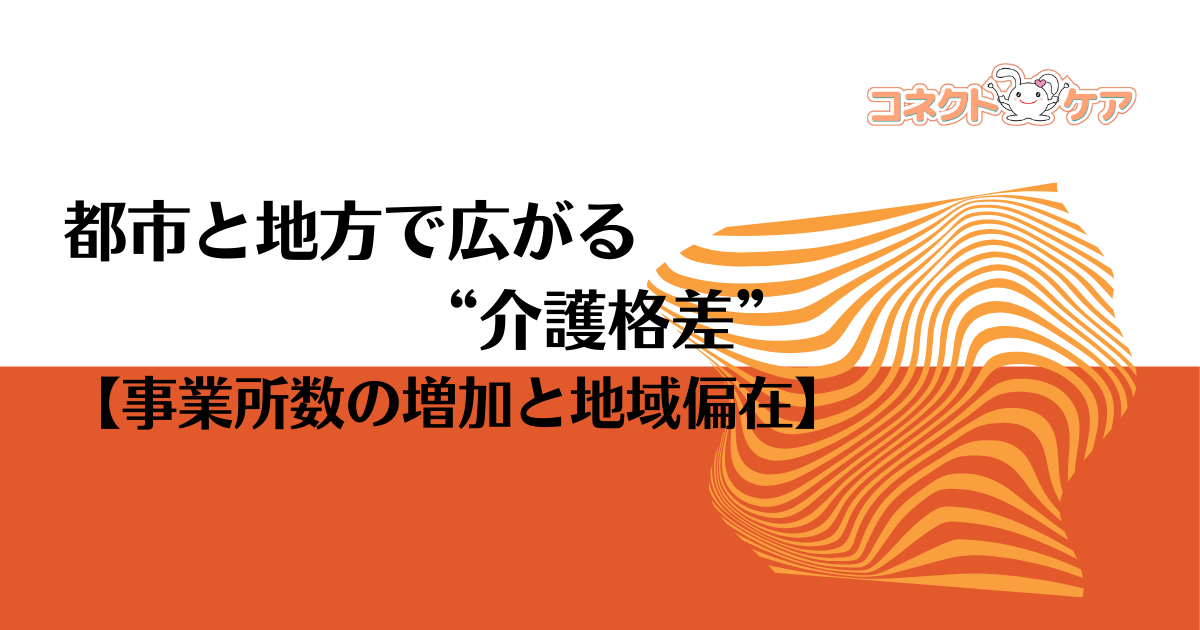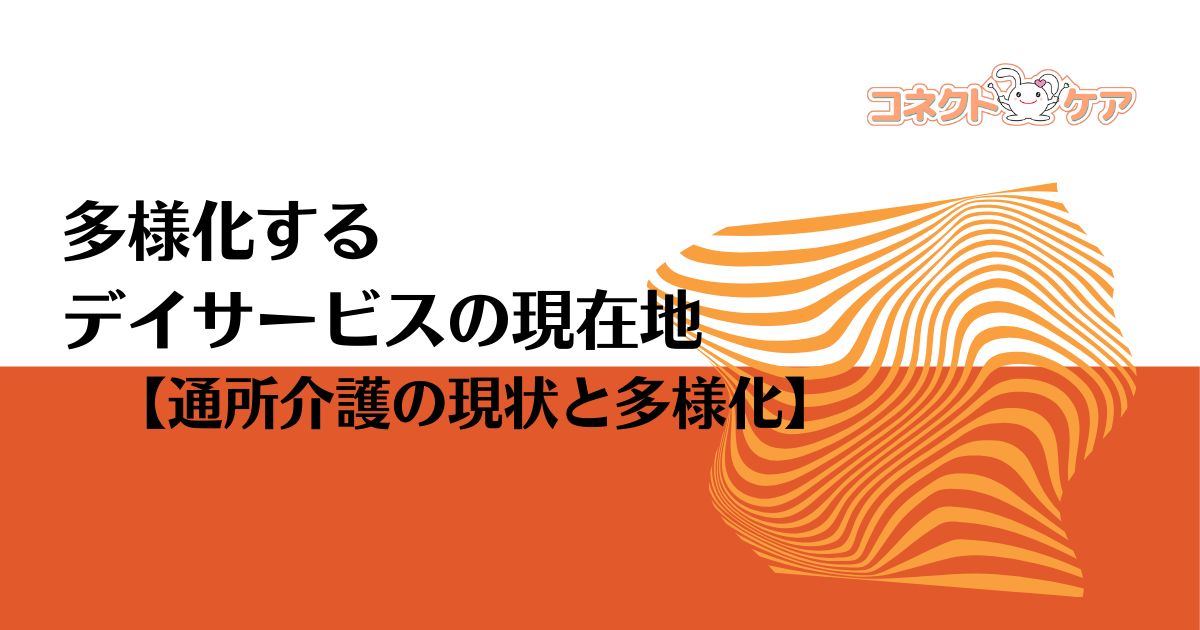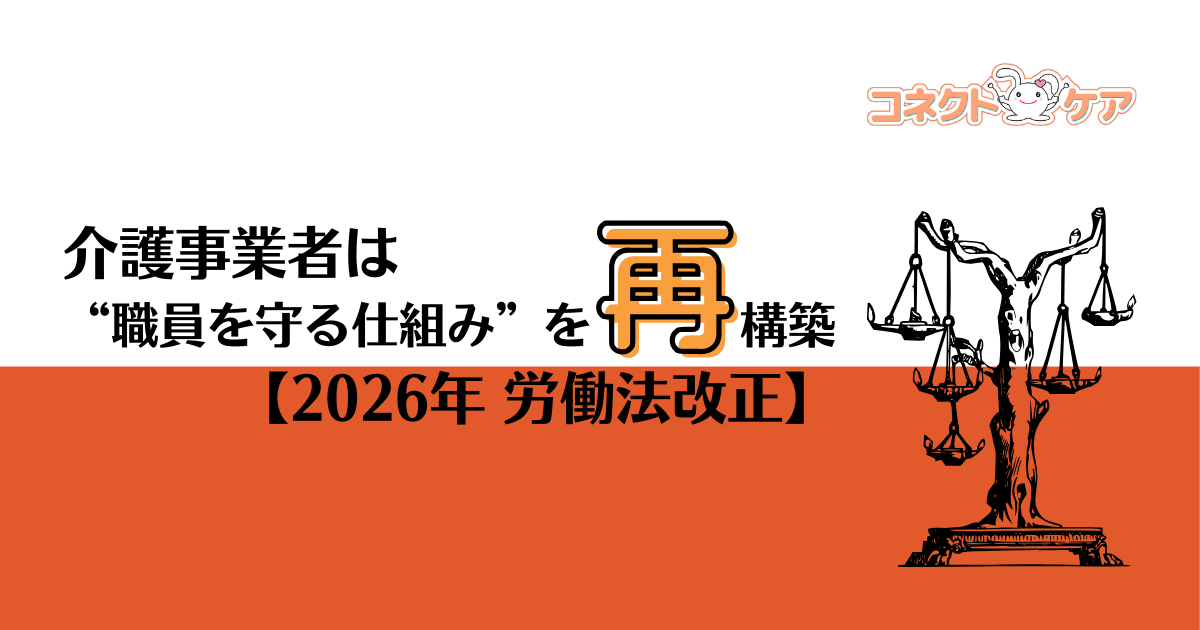LIFEの入力項目と実際の記録との連動イメージ

LIFE(科学的介護情報システム)を活用するには、通所介護事業所が日々記録している情報を適切に整理し、所定の項目に沿って入力・提出する必要があります。しかし、LIFEの入力項目は専門用語も多く、現場の記録とどう結びつければよいか悩まれる方も多いのではないでしょうか?本記事では、LIFEに必要な入力項目を整理したうえで、現場の介護記録とどのように連動させていくべきかを解説します。
LIFEで求められる主な入力項目
LIFEでは、ADL・栄養・口腔・排泄など、利用者の生活機能に関する多角的な評価が求められます。これらの項目は科学的根拠に基づいた支援の材料として使われるため、正確かつ継続的な記録が必要です。
基本項目と評価指標の全体像
LIFEで求められる主な項目には以下があります:
- ADL評価(Barthel Index):移動・排泄・食事・更衣など10項目
- 口腔状態(OHATスコア):唇・舌・歯・義歯・歯茎の状態など
- 栄養状態(MNAなど):BMI、食事量、体重減少の有無
- 排泄状況(自立度)
- 認知症の周辺症状(BPSD)や重症度
- 個別機能訓練計画に基づく評価項目(該当する加算を算定している場合)
これらの項目は単に一度評価するだけでなく、定期的な再評価と、そのデータ提出がLIFEの運用には求められます。
提出単位と頻度
通所介護では、月に1回以上のデータ提出が原則とされています。対象者の人数に対して、提出率が一定水準(例:8割以上)に達していないと加算の算定が認められないケースもあるため、提出のタイミングと対象者の管理も重要です。
現場の記録とLIFEの項目の関係
LIFEの入力に必要な情報の多くは、すでに現場で日々記録されているものと重なっています。ただし、評価基準や様式の違いにより、そのままではLIFEに使えないケースも多いため、事前のすり合わせが必須です。
現場記録から転記可能な情報とは
たとえば、毎日のバイタル記録や食事摂取量、排泄の状態、機能訓練の記録などは、LIFE提出に活用できます。しかし、形式や項目名が異なるため、LIFE用に整理された形で記録されている必要があります。
例:
- 「食事完食」→ MNA評価の一部に該当
- 「トイレ誘導あり」→ 排泄自立度に反映
- 「体重の記録」→ 栄養状態の評価に必要
二重入力を防ぐ記録設計のポイント
現場記録とLIFEの提出項目を分けて管理してしまうと、記録が重複し職員の負担が増大します。対策としては:
- 記録様式にLIFE入力と同じ項目を含める
- 評価者(看護師やリハ職)を明確にし役割分担
- LIFE提出に必要な記録項目を見える化(マニュアル整備)
記録ソフトがLIFE出力に対応している場合は、通常の記録がそのまま提出データに変換されるため、導入のメリットが非常に大きくなります。
LIFE入力を効率化するための工夫
LIFEの入力業務を効率化するには、記録方法の工夫とICTの活用がカギです。人手に頼らない仕組みづくりを進めることで、現場負担を抑えつつ継続的な運用が可能になります。
記録ソフトと連携した提出体制
LIFEに対応した記録ソフトであれば、以下のような機能が提供されているケースが多いです:
- 記録と連動した自動集計・CSV出力
- 提出済み・未提出データの管理
- 提出対象者の一括抽出・履歴管理
こうした機能により、記録ミスや提出漏れのリスクを大幅に削減できます。特に、提出対象者数が多い中規模以上の通所介護事業所では導入効果が高くなります。
職員間での共有とフィードバック体制
LIFE入力を一部の職員だけに任せると、属人化や記録漏れが起きやすくなります。職種を超えた情報共有と、提出内容に対するフィードバック体制を整えることで、ケアの質向上にもつながる「LIFEの活用」が実現します。
まとめ
LIFEの入力項目は、通所介護における日々の記録と密接に関連しています。大切なのは、日々の記録とLIFE提出を一体化した記録設計を行うことです。ICTの活用と記録の見直しを通じて、現場の負担を抑えながら質の高いデータ提出を実現しましょう。

.png)